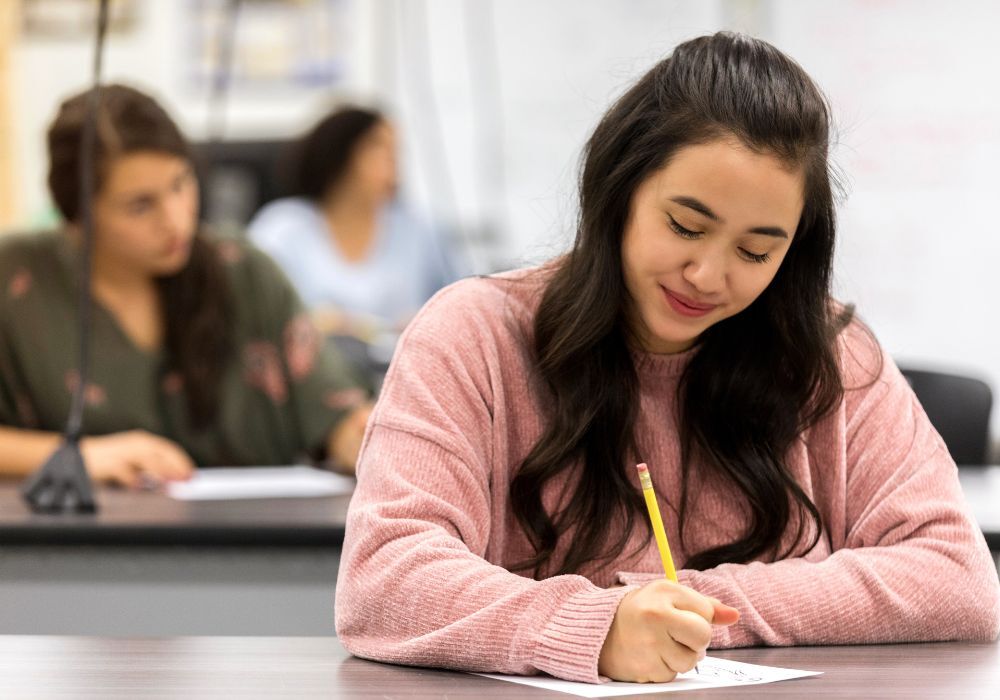留学に必要なTOEICスコアとは?合格ラインと勉強法を徹底解説
2025.08.05
留学を考え始めたとき、多くの人がまず気になるのは英語力をどう証明するかという点です。
TOEICのスコアは就職や社内評価で広く使われますが、留学でどの程度役に立つのかは意外と知られていません。
この記事では、TOEICの活用場面と限界、TOEFLなど他試験との違い、効果的な学習法やスケジュール例まで具体的に解説し、あなたが次の一歩を迷わず踏み出せるよう道筋を示します。
留学に必要なTOEICスコアの目安
TOEICを留学にどう使うかは、交換留学か正規留学か、そして受け入れ先の方針によって異なります。
一般的に交換留学では学内選考の参考指標としてTOEICが用いられることがあり、600~700点程度を目安に求められる例が見られます。
ただし正式な出願要件は大学やプログラムごとに違うため、最新の募集要項で必ず確認し、必要に応じて他試験も準備しておくと安心です。
交換留学と正規留学での必要スコアの違い
交換留学は提携校間の単位互換を前提とするため、学内基準としてTOEICの目安点が示されることがあります。
対して学位取得を目指す正規留学では、アカデミックな読み書きや講義参加に耐える力を測るため、TOEFLやIELTSが必須になることが多いです。
つまりTOEICは「交換留学の足切り突破」には役立ちますが、正規留学の本出願では別試験が求められることを想定して計画を立てましょう。
国や大学ごとのスコア基準の例
アメリカやカナダの大学では、英語要件にTOEFL iBTやIELTSを指定するケースが主流で、学部であっても一定のライティングやスピーキング要件が設けられます。
ヨーロッパの一部交換留学では、内部選考にTOEICの点数を参照する大学もありますが、履修登録後の英語授業で求められる力はTOEICの得点だけでは測れません。
自分の志望先がどの試験を重視するかを洗い出し、TOEICの勉強と並行して必要試験の準備を早めに始めるのが得策です。
TOEICとTOEFLの違い
TOEICは主にビジネスや日常場面のリスニングとリーディングを測る試験で、設問は選択式が中心です。
TOEFLはアカデミックな文章の理解に加え、ライティングとスピーキングで自分の考えを論理的に表現する力まで評価します。
出願要件に合致するかどうかが最重要なので、目的に合わせて試験の選び方を最初に決めてしまうと学習がぶれません。
出題形式と評価対象の比較
TOEICは時間あたりの問題数が多く、設問パターンに慣れると得点が安定しやすい特徴があります。
対してTOEFLは統合型問題があり、読んだ内容を要約して話す、聞いた内容を踏まえて書くといった高次タスクが出題されます。
どちらも英語力の一面を測定しているに過ぎないため、志望先が求める力と試験の評価軸が一致しているかを常に点検しましょう。
留学に向いている試験の選び方
短期の交換留学で学内選考を突破したいなら、締切までの残り時間と現状スコアからTOEICの伸び幅を現実的に見積もるのが有効です。
正規留学で出願点が定められているなら、TOEFLやIELTSの受験計画を先に立て、TOEICは語彙やリーディングの土台作りとして活用する方法があります。
いずれにしても試験選定は「要件との整合性」「学習リソース」「試験日程」の三点で判断すると失敗しにくくなります。
TOEIC対策で押さえるべき学習法
学習の起点は現在地の可視化です。
公式問題集で模試を1回分解き、パート別の正答率と所要時間を記録すると、弱点が一目でわかります。
そのうえで頻出のリスニング・リーディングの基礎を固め、毎週のサイクルで改善点を検証する仕組みを作ると効率が上がります。
リスニング力を伸ばす勉強法
ディクテーションで音のつながりを可視化し、シャドーイングで音声変化に慣れるのが王道です。
聞き取れない箇所は音素レベルの聞き分けに問題があることが多く、速度を落として正確性を優先してから元速に戻すと定着します。
毎日の短時間学習でも継続すれば、設問の先読みや設問タイプごとの注意点が自然と身体に染み込みます。
リーディングと単語強化のコツ
長文では設問先読みと段落要旨の把握で時間を節約します。
語彙は派生語と品詞転換まで一緒に覚えると、設問の文法判断に強くなります。
難問で時間を溶かすよりも、解ける問題を確実に得点化する戦略が全体スコアを押し上げます。
短期間でスコアアップする勉強スケジュール例
期限が決まっているときは、学習計画を「週のリズム」と「毎日の固定枠」に落とし込むと続けやすくなります。
模試・復習・重点改善の三段構えを1週間で回すだけでも、数値は確実に動きます。可視化されたチェックリストと学習ログをセットにすると、達成感が積み重なりモチベーションが維持できます。
3か月で目標達成するための学習計画
1~4週は基礎固め期として、音読・語彙・設問パターンの確認を中心にします。
5~8週は演習量を増やし、毎週末の模試で時間配分を最適化します。
9~12週は弱点特化の仕上げに集中し、試験2週間前からは本番時間での通し演習を増やしてコンディションを整えます。
忙しい社会人向けの時間活用法
通勤時間はリスニングのゴールデンタイムなので、倍速と通常速を切り替えて耳を鍛えます。
昼休みや移動の隙間は1セット5分の文法・語彙ドリルに当て、夜は15分の弱点復習で締めると無理なく回せます。
週末のどちらかで模試を1回分こなし、翌日に復習する二段構えが効果的です。
よくある失敗と回避策
学習が続かない最大の理由は、計画が細かすぎるか抽象的すぎることです。
完璧主義に陥ると未達が続き自信を失いやすく、逆に大雑把すぎると何をすればよいか迷ってしまいます。
適正難度のタスクを日々の固定枠に組み込み、達成したら小さく自分を褒める仕組みを用意しましょう。
「計画倒れ」を防ぐ工夫
計画は「時間」「教材」「結果指標」の三点セットで作ると実行性が高まります。
例えば「平日20分・公式問題集・Part3正答率80%」のように定義すれば、やるかやらないかの迷いが消えます。週初めに計画、週末に達成度チェックという固定リズムにするだけでも継続率は上がります。
模試の活用で伸び悩みを突破
模試は得点の確認だけでなく、改善仮説を立てる材料です。
間違えた問題を「語彙不足」「設問の読み違い」「時間切れ」にラベリングすると、翌週の学習計画に直接落とし込めます。
復習ノートに「原因→対策→次回の行動」を1行で書くと、同じ失敗を繰り返しにくくなります。
まとめ
留学の出願可否は志望先の要件が最優先で、交換留学ではTOEICが目安として役立つ一方、正規留学ではTOEFLやIELTSが求められる傾向があります。
あなたの目的と期限から試験を選び、模試→弱点特定→改善の週次サイクルで学習を回せば、短期間でも着実な伸びが期待できます。
英会話力の実戦練習や個別の課題発見には、講師の質とカリキュラムに定評のあるシェーン英会話の無料体験レッスンを活用し、自分に合う学習計画を一緒に設計してみてください。